
産休後に職場復帰する予定なんだけど、うちの子…保育園にちゃんと入れるかな?

うんうん、保育園の入園通知が届くまではハラハラするよね。
でもね、実は「ここは外せない!」っていう大事なタイミングがあるんだよ!

えっ、そんなのあるの!? ぜひ教えて〜!

今回はその「保育園に入りやすいタイミング」について、分かりやすく解説するね。
「0歳から預けるのはかわいそう?」「1歳だと希望の園に入れないって本当?」
保活を始めたばかりだと、いつ預けるのがベストなのか分からず、不安になりますよね。
この記事では、2児のママで子どもが0歳の時から保育園に預けて働いていた経験と小規模保育園での勤務していた経験を元に以下のような疑問を解消していきます。
- 0歳・1歳・2歳で預けるときのメリット・デメリット
- 保育園に入りやすい時期とは?
- ワーママのリアルな保活体験談
- 後悔しない預け先の選び方

我が家の保育園の経歴について

ここでは、我が家の子どもたちの保育園経歴をご紹介します。
認可外・認可・新設園と、保育園フルコースを経験したからこそお伝えできることがたくさんあります!
- 生後6か月〜11か月:認可外保育園に入園
- 11か月〜5歳(年中):認可保育園に転園
- 6歳(年長)〜:引っ越しを機に新設保育園に転園
- 生後2か月〜11か月:認可外保育園に入園
- 11か月〜3歳(年少):認可保育園に転園
- 4歳(年中)〜:引っ越しを機に新設保育園に転園
我が家は、
無認可保育園 → 認可保育園(歴史あり) → 新設保育園と、さまざまな保育園を経験してきました。
そのため、保育園選びや入園時期について、実体験に基づいたお話ができます。
また、私自身が小規模保育園で勤務していたこともあり小規模保育園で働く先生方のリアルな声をお届けすることができます。
この記事では、「職場復帰を目指すご家庭にとって、後悔しない保育園の預けどきとはいつか?」について、わかりやすくお伝えしていきますね。
保育園の種類と違い:認可保育園と認可外保育園の特徴と選び方

保活を始めるなら、まず知っておきたいのが「保育園の種類」。
保育園は主に【認可保育園】と【認可外保育園】の2種類があります。
入園のベストタイミングを考える前に、それぞれの特徴をしっかり押さえておきましょう。
認可保育園とは?自治体が認めた安心の保育施設
認可保育園とは、国が定めた基準(施設の広さ・保育士の人数・給食の提供など)を満たし、各自治体の認可を受けて運営されている保育園のことです。
運営費の多くは自治体の補助金でまかなわれており、保育料は世帯の収入に応じて決まるのが特徴です。
認可保育園の主な特徴
- 保育料が所得に応じて決まるため、家計にやさしい
- 給食の提供が義務づけられている
- 国や自治体の基準を満たした安心の施設
- 保育士の配置基準が法律で決められている
地域によっては入園希望者が多く、倍率が高くなることにより待機児童になることもあります。
認可外保育園とは?柔軟さが魅力のもうひとつの選択肢
認可外保育園とは、国や自治体の「認可基準」を満たしていないものの、独自の運営基準でサービスを提供している保育施設のことです。
最近では「企業主導型保育園」など、多様なスタイルが登場しています。
認可外保育園の主な特徴
- 開園時間や曜日の融通がききやすい
- 保育料は高めに設定されていることが多い
- 空きがあれば、比較的すぐに入園できる可能性が高い
- 施設や保育士配置の基準は園によって異なる

私も働き始めたばかりのころ、認可に入れず認可外に預けていました。
保育料は正直高かったけれど、「預け先がない」っていう不安から解放されて、心の余裕ができたのは本当に大きかったです!
保育園は何歳から預けられる?基本情報を確認

保育園は、0歳から入園が可能です。
多くの保育園では、生後6か月以降の赤ちゃんを受け入れていますが、なかには生後2か月から預けられる園もあります。
ただし、入園できる月齢は園ごとに異なるため、事前に確認しておくことがとても大切です。

年度途中の入園など、タイミングによっては募集していないケースもあるので、気になる園があれば早めに問い合わせておくのがおすすめです。
保育園は何歳から入れるのがベスト?4月入園で仕事復帰を目指す
待機児童の多い昨今、保育園に入れるかどうかで職場復帰のタイミングが大きく左右されますよね。
家庭の事情や自身のキャリアにも関わる重要な選択ですが、「絶対に保育園に入れて、職場復帰したい!」という方には、
▶一斉入所(4月)× 0歳児クラスの入園を強くおすすめします。
このタイミングを逃すと、次にいつ入園できるかは読めなくなってしまうため、早めに役所で申込スケジュールを確認しておくことが大切です。

受け入れ枠が一番多い、0歳児の4月入園を狙うのが安心だよ!
わが家では第1子を生後半年で入園させました。
哺乳瓶拒否で、ミルクを飲まず入園に対して不安で何度も泣いたことがあります。
しかし、保育園がなかなか決まらず毎月不安定な日々を過ごす中で無認可保育園への入園が決まったときは、ホッとしたことを覚えています。
無認可保育園で、園児が少なかったものの入園してすぐに風邪をひき発熱や風邪にはとても悩まされ、子どもから風邪が移るなど家族の健康維持も大変でした。
保育園への入園は、
家庭の状況お子さんの性格によって、ベストなタイミングは異なります。
ぜひ、無理のないスケジュールで保活を進めてくださいね。
保育園に一番入りやすいのは「0歳児クラス」
なぜ0歳児クラスが入りやすいの?
他の年齢は、前年度から在籍している園児が枠を占めているため、新規募集人数が限られて倍率が高くなる傾向にある。
0歳児クラスは前年からの「持ち上がり」がないため、すべての枠が新規入園希望者向けに開放されている。
\年齢別の入園枠の違いを表にまとめてみました!/
| 年齢クラス | 募集枠の多さ | 特徴 | 入園難易度 |
|---|---|---|---|
| 0歳児 | ◎(最も多い) | 全員が新規入園 | ★☆☆(入りやすい) |
| 1歳児 | △(少ない) | 0歳児クラスからの持ち上がり多数 | ★★★(競争率高め) |
| 2歳児 | ×(ほぼなし) | ほとんどが継続児で埋まっている | ★★★(かなり難しい) |
| 3歳児 | ○(増えやすい) | 転園や幼稚園移行による空きあり | ★★☆(比較的入りやすい) |
「持ち上がり」っとは、たとえば前年0歳で入園した子が1歳に進級してそのまま園に残ることです。つまり、すでに席が埋まっている状態ですね。
次に入りやすいのは「3歳児クラス」
0歳からの入園が難しい場合や、育休の都合が合わない場合は、3歳児クラス(年少)が次の狙い目です。
- 保育士配置基準が変わり、受け入れ枠が広がりやすい
- 幼稚園への転園や転居による退園などで空きが出やすい
- 「保育園 or 幼稚園」を選ぶ家庭が増えるため入園希望者が分散する

3歳になると子どもの個性も見えてきて、家庭のライフスタイルに合わせた園選びがしやすくなるよ!
出産前から準備できることを進めよう
育児に追われながら、復帰や入園準備を進めるのはとても大変。
でも、出産前だからこそできる準備もたくさんあります。
- 保育園の見学
- 説明会への参加
- 役所での保活相談
- 地域の保育園の情報収集
事前に把握できる情報は出産前から準備していきましょう!
保育園で感染症が流行している場合があります。
その際は無理に見学せず再度日程調整をお願いするようにしましょう。
出産前に準備したい保活チェックリスト表がありますので、参考にしながら準備進めてくださいね。
▼出産前に準備したい保活チェックリスト
| チェック項目 | 内容 | メモ欄 |
|---|---|---|
| 希望エリアの園を調べる | 自宅・職場近く、通いやすさなどを基準に候補を絞る | 例:駅から徒歩10分以内など |
| 各園の見学予約をする | 園の雰囲気・保育方針・先生の対応を見る | ネット予約可か電話かもチェック |
| 募集要項を確認する | 募集人数、入園対象年齢、必要書類など | 市区町村のHP or 園の配布資料で確認 |
| 保育必要度(指数)を調べる | 自分の就労状況や家庭状況の加点をチェック | 育休明け・きょうだい在園などは加点対象か |
| 申し込み期間を把握する | 自治体の締切日、説明会の日程などを把握 | 地域によって異なるので注意 |
| 必要書類を揃える | 就労証明書、申請書類など | 会社に早めに依頼する必要あり |
| 入園後の働き方を決める | 復帰時期や勤務時間、サポート体制を考える | 時短勤務、送迎の分担なども検討 |
| 育休期間と復帰時期を見直す | 0歳4月入園に合わせるための逆算が重要 | 例:4月入園→慣らし保育後復帰 |
| 夫婦で役割を話し合う | 送迎・発熱時の対応・園行事など | 共働きだからこそ分担がカギ! |
保活のスケジュールや申込時期の目安
「保活って、いつから始めればいいの…?」
そう思いながらも、気づけば申し込み締切が迫っていた…という声も少なくありません。
保育園の申し込みは自治体ごとに時期や手続きが異なるため、事前のスケジュール把握がとても重要です。
ここでは、一般的な保活の流れやスケジュールの目安を紹介しますので、安心して準備が進められるようチェックしておきましょう。
保活を始めるベストな時期は?
- 妊娠中から情報収集を開始しましょう
- 人気の園は見学予約がすぐ埋まるため、早めの行動がカギ
- 復職時期・育休明けを見据えて「いつ預けたいか」から逆算
4月から入園を希望する場合は、出産前から情報収集を行い保育園入園希望の申込日を逃さないようにしましょう!

早めに準備をすることで安心して子育てに集中できますよ
自治体の申込時期と流れ(2025年度(令和7年度)4月入園の場合)
- 結果通知:12月〜1月(自治体により異なる)
- 入園準備:2月ごろから説明会・必要品の準備が始まる
- 申し込み受付:多くの自治体で9月~11月ごろに一次募集
参考に、大阪市の申込日を紹介します。
1次調整(令和7年4月1日からの利用希望)
- 令和6年9月4日(水曜日) 申込書類の配付開始
- 令和6年9月9日(月曜日) 募集予定人数の公表、受付日時のオンライン予約開始
- 令和6年10月1日(火曜日)~15日(火曜日) 受付期間
- 令和6年10月28日(月曜日) 申込状況公表予定
- 令和6年11月15日(金曜日) 希望施設等の変更及び不足書類等の追加提出期限
- 令和7年1月27日(月曜日) 結果通知発送 29日(水曜日)以降順次到着予定
2次調整(令和7年4月1日からの利用希望)
大阪市
- 令和7年1月10日(金曜日)~2月7日(金曜日) 受付期間
- 令和7年2月27日(木曜日) 結果通知発送 3月3日(月曜日)以降順次到着予定
自治体によってスケジュールが異なりますので、ホームページを見てスケジュールを確認するようにしましょう!
確認場所が分からない場合は、自治体に電話をしましょう!
希望の保育園に入るためにできること
「この園に入りたい!」と思っていても、希望どおりにいかないのが保活の現実…。
だからこそ、少しでも合格の可能性を高めるために、いまできる準備をしておきたいところです。
ここでは、希望園に入るためのポイントや、不承諾だった場合の対策についても紹介します。
申し込み書類の準備
申込書類の準備を行いましょう!
私が住んでいた自治体では、第1希望、第2希望…のようき希望の順に園の名称を記載する仕様となっていました。
第1希望、第2希望のように希望順に記載できる場合は、第1希望に園の名称を記入するようにしましょう。
点数制度と優先順位の考え方
入園を申し込むためには、勤務状況などによる保育利用調整(点数)が高いことが条件となります。
自治体に、保活について相談した際に希望園の人気度やどんな働き方をしている家庭が多いかなど聞ける範囲で確認をしていきましょう!
また、保育園に入園できる範囲の点数なのか、厳しい点数なのかも合わせて確認をしましょう。
不承諾だった場合の選択肢
希望園に入れなかった場合、
- 次年度に持ち越す
- 無認可保育園に預ける
- 空いている保育園がないか確認し、入園を希望する
など、希望園に入園できなかった際の対策も合わせてご家族で話し合っておきましょう!
無認可保育園への入園も希望者が多く、保育園の当選結果が届いたその日から申し込みが殺到するなども考えられます。
悩んでいるうちに、「申し込みが終了した」なども考えられますので、後悔しないためにも準備・ご家族での話し合いを怠らないようにしていきましょう。
保育園に年度途中で入園する方法と可能性とは?

結論から言うと、保育園に年度途中で入園することは可能ですが、期待しすぎない方が賢明です。
特に4月の一斉入所で多くの園が定員に達してしまうため、その後に空きが出ることは非常にまれです。
特に0歳児クラスは、もともと受け入れ枠が限られているため、途中入園の募集がないケースも少なくありません。
そのため、入園が決まるまで「いつ入れるかわからない」と不安を抱え、毎月待機し続ける状況が続くことが多く、精神的なストレスが大きい家庭も少なくないのが現実です。
くるみんの実体験
実際、我が家も年度途中での入園を何度も申し込みましたが、結果はすべて不合格でした。
当時は認可外保育園に預けながら共働き(保育指数は高め)という状況にもかかわらず、途中入園の壁は想像以上に高いと感じました。
年度途中の入園は「可能性ゼロではない」とは言えますが、あくまで例外的なケースとして捉え、基本的には4月入園を前提にスケジュールを立てることを強くおすすめします。
- 希望園の空き状況を毎月チェック
- 無認可や認可外保育園も選択肢に入れる
保育園の途中入園を目指すには?確率と対策ポイント

実は、園の環境が整ったタイミングで、0歳児でも途中入園の枠が増えることがあります。
例えば、「保育士が増えた」「施設が広がった」などの理由で、追加の受け入れ枠が出るケースです。
ただし、途中入園は希望者が多いため、入園のハードルは高めです。
とはいえ、申し込みをしなければ入園の可能性はゼロのまま。少しでもチャンスをつかむためにも、申し込みだけはしておくことをおすすめします。

自宅から遠い園にしか空きがないというケースもありますよね。
毎日通う園だからこそ、通園距離や交通手段についてもしっかりと検討しておくことが大切です。
- 更新日時や申込期限を見逃さないこと
- 自治体が発表する最新の受け入れ情報を常にチェック
- 役所のホームページや保育課に直接確認することが確実
0歳児で保育園に入れなかったら小規模保育園を検討しよう!

0歳児で預ける踏ん切りがつきません。
0歳児を逃すと、もう保育園に入れるタイミングはないのでしょうか?

気持ち、すっごくわかりますよね。0歳児って、まだまだ赤ちゃん。
「こんなに小さいのに、離れるなんて…」と思って当然です。
でも、安心してくださいね。
たしかに0歳児が一番入りやすいタイミングではありますが、それを逃しても、チャンスはあります。
もし0歳児での入園が難しかった場合、小規模保育園も選択肢に入れることをおすすめします。
小規模保育園は定員数が少ないため、空きが出やすいケースもありますし、比較的柔軟な対応をしてくれることが多いです。
また、園の規模が小さい分、1人1人にかける時間や手厚いサポートが期待できることも大きな魅力です。地域によっては、小規模保育園の選択肢も豊富にあるので、ぜひ検討してみてくださいね。
小規模保育園の選び方のポイント
「小規模保育園ってたくさんあるけど、どうやって選べばいいの?」
「転園もあるって聞くし、失敗したくない…」
そんな不安を感じているママ・パパのために、後悔しない園選びのポイントをわかりやすくまとめました。
たとえば小規模保育園を選ぶときは、
- 1日の過ごし方
- 食事やお昼寝の環境
- 見学したときの印象
- 駐車場や駐輪場の有無
- 自宅や職場からの距離
- 園の保育方針や先生の雰囲気
- 園の近くに公園や遊べる場所があるか?
- 毎日の送り迎えのしやすさ(徒歩、自転車、車など)
などをチェックしておくと安心です。
小規模保育園は、園庭などがない場合が多く近くの公園などに遊びにいくことも多々あります。
園の雰囲気などの合わせて周辺の環境についてもチェックしておきましょう!
園の雰囲気、先生の相性はもちろんのことですが、直観も大事にしてください。
なんとなく、「合わない気がする…」などのように不安に感じることがあれば無理に申し込まないことも大切です。

他園と比較するためにも、できれば複数の園を見学して、雰囲気を比べてみてくださいね。
小規模保育園とは?対象年齢・定員・メリット・デメリットをわかりやすく解説
小規模保育園のメリット・デメリットについて解説していきます。
▼小規模保育園のメリット・デメリット
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 家庭的な雰囲気少人数制でアットホームな環境。 | 3歳以降の転園が必要小規模保育園は0~2歳児が対象で、3歳からは他の園への転園が必要。 |
| 一人ひとりに寄り添った保育保育士の目が行き届きやすく、個別対応が可能。 | 設備が限られている園庭や遊具がない園も多く、遊びの幅が狭まることがある。 |
| 異年齢児との交流異なる年齢の子どもたちが一緒に過ごすことで、社会性が育まれる。 | 行事が少ない大規模園に比べて行事の数が少なく、盛り上がりに欠けることがある。 |
| 保育士の配置が手厚い国の基準より多く配置されることがあり、手厚い保育が受けられる。 | 保育士のスキルにばらつきがある場合も職員の経験やスキルに差があることがある。 |
| 感染症リスクが低い少人数のため、感染症のリスクが比較的低い。 | 保育参観の機会が少ない保育参観や行事が少なく、園での様子を見る機会が限られる。 |
小規模保育園が向いている家庭とは?
小規模保育園は、以下のような家庭に向いています。
- 少人数の園を希望する家
- 0~2歳児の手厚い保育を希望する家庭
- 家庭的な雰囲気の中で子どもを育てたい家庭
- 保育士との密なコミュニケーションを重視する家庭
ただし、3歳以降の転園が必要となるため、将来的な保育計画を立てる際には注意が必要です。
小規模保育園の特徴
小規模保育園は、0歳~2歳の乳幼児を対象とした定員6〜19名以下の少人数制の保育園です。
少人数ならではの家庭的な雰囲気と、丁寧な保育が魅力。最近では、待機児童対策としても注目されています。
小規模保育園が途中入園のチャンスを提供する理由
小規模保育園は、0歳児~2歳児を対象としており、3歳児(年少)になるタイミングで他の園に転園しなければならないため、転園を考える家庭が多いです。
そのため、2歳児が卒園する前後で空きが出やすい傾向があります。
その結果、小規模保育園では他の保育園に比べて、途中入園のチャンスが高くなるのです。
園児の人数が少なく、アットホームな雰囲気の中で過ごせるのも小規模保育園の魅力。
転園があるからといって最初から選択肢を外すのはもったいないですよ。

見学に行って雰囲気を確かめてみてくださいね。
小規模保育園のデメリットとは?入園前に知っておきたい注意点
小規模保育園のデメリットについて解説していきます。
改めて保活する必要がある
小規模保育園の大きなデメリットは、3歳児のタイミングで再び保活を行う必要があることです。
3歳以降は小規模保育園に在籍できないため、次の進路(保育園または幼稚園)を選ばなければなりません。
また、転園先を探す際には、自治体の保育利用調整(点数)による選考が行われます。
入園時に高得点で入れた場合でも、転園時には状況によって点数が変動するため、再度注意が必要です。
点数が下がる可能性のあるケース
- ご主人が退職・転職活動中
- 妊娠中で産休に入っている
- フルタイムから時短勤務に変更した
- 本人が仕事を辞めた、または転職活動中
保育園の入園は「点数の高い家庭が優先される」ため、点数次第では希望の園に入れない可能性もあります。
そのため、再度保活を始める際には「保育園」と「幼稚園」の両方を視野に入れ、早めに情報収集して準備を進めることが大切です。
小規模保育園で実際に働いた感想

園児ひとりひとりとしっかり向き合って保育と向き合いたくて小規模保育へ転職しました。

園児と丁寧に向き合っていける環境に就職したく小規模保育を選択しました。

保育園の優しい雰囲気と園児ひとりひとりに向き合う環境に魅力を感じ転職しました。
パート勤務ですが、保育に関われていることがとても嬉しい
「園児ひとりひとりに向き合える保育園に関わっていきたい」
「自身の家庭や働き方も大切にしながら、保育という仕事にも関わっていきたい」
上記のように、園児にしっかり向き合っていきたい思いを抱えて小規模保育園へ転職してきた先生が多くいらっしゃいました。
小規模保育園の魅力の1つである、「園児ひとりひとりに向き合っていける点」に魅力を感じている点から
小規模保育園だからこそ、子どもの個性を大事にし豊に育んでいけると感じていました。
その一方、私自身もそうでしたが調理員として無資格で関わることができるなど、資格の有無に関して気になる方には不向きな点もあります。
小規模保育園に預けるメリットも大きいですが、デメリットと照らし合わせ子育ての価値のもと選択していくことが大切です。
小規模保育園からの転園先の探し方
小規模保育園は3歳までの保育施設のため、それ以降は転園が必要になります。
でも、「次にちゃんと入れるの?」「また保活するの…?」と不安になりますよね。
ここでは、転園先をスムーズに見つけるための3つのポイントをご紹介します。
連携園(受け皿となる保育園)があるか確認する
小規模保育園の中には、3歳以降の「受け皿」となる連携園が決まっているところもあります。
連携園があると、
- 優先的に転園できる
- 引き継ぎがスムーズ
- 園の雰囲気が似ていて馴染みやすい
といったメリットがあります。

うちの地域では、連携園のある小規模園はやや入りやすく、転園の不安も少なかったですよ♪
園見学のときに、「卒園後の進路」「連携園の有無」は必ず確認しておきましょう。
※連携園とは、小規模保育園の卒園後に優先的に受け入れてくれる保育園のこと。自治体によって制度や有無が異なります。
情報収集は“年少クラス”の前年度から
転園先の申し込みは、2歳児クラスの秋〜冬ごろ(自治体によって異なる)に始まります。
参考:大阪市申し込みスケジュール
そのため、年少になる年度の前年の春〜夏には情報収集をスタートするのがおすすめ。
1次調整(令和7年4月1日からの利用希望)
- 令和6年9月4日(水曜日) 申込書類の配付開始
- 令和6年9月9日(月曜日) 募集予定人数の公表、受付日時のオンライン予約開始
- 令和6年10月1日(火曜日)~15日(火曜日) 受付期間
- 令和6年10月28日(月曜日) 申込状況公表予定
- 令和6年11月15日(金曜日) 希望施設等の変更及び不足書類等の追加提出期限
- 令和7年1月27日(月曜日) 結果通知発送 29日(水曜日)以降順次到着予定
2次調整(令和7年4月1日からの利用希望)
大阪市
- 令和7年1月10日(金曜日)~2月7日(金曜日) 受付期間
申し込みスケジュールは各自治体のHPに掲載されていますので、受付期間までに
- 園の見学
- 申し込み方法の確認
- 保育利用調整基準の点数
- 申し込み前に申込用紙を窓口で確認してもらう
(申込用紙に不備があると、申し込みが行えないため事前に確認しましょう。)
について確認を行い、申込日までに準備を行っていきましょう!
私の自治体では、担当部署の担当により言っていることが異なっていることがありました。
不安な場合は、複数回確認するようにしましょう!

自治体によっては、印鑑などが必要な場合もあります。
申込日に必要な持ち物があれば事前に確認しておきましょう!
幼稚園 or 保育園?家庭に合った選択をしよう
3歳になると、「保育園に転園するか?」「幼稚園に切り替えるか?」という選択も出てきます。
\こんな判断基準も参考に/
| 比較項目 | 保育園 | 幼稚園 |
|---|---|---|
| 保育時間 | 長め(〜18時など) | 短め(14時前後まで) |
| 対象 | 働く保護者向け | 保護者が在宅でもOK |
| 預かり保育 | 一部あり(自治体による) | 延長保育を設ける園もあり |
| 給食 | あり | 弁当 or 給食(園による) |
私が子どもを保育園に預けて復帰したときの本音
「ハイハイもまだできない娘を預けて仕事復帰する意味って、なんなんだろう……」
そんなふうに悩んでいた私。
預けた当初は離れるのが辛すぎて、泣きながら友人に電話をしたこともありました。
職場復帰後は、フルタイム勤務に加えて、夜泣き、授乳……。今思えば「よく乗り越えたな」と自分でも思います。
でも、保育園の友達や先生とのふれあい、行事を通して成長していく娘を見て、「預けてよかった」と思える日々も少しずつ増えていきました。
復帰直後は目まぐるしくて本当に大変。でも、仕事をすること自体が自分にとって“息抜き”にもなっていたと気づいたんです。
私はもともとキャリアに自信がなかったのですが、働きながら経験を積み重ねることができたことで、
「子どもたちを育てていくうえでの安心材料ができた」そんなふうに思えるようになりました。
私は、認可外保育園から認可保育園へと預けながら仕事復帰したことは、結果的に最善の選択だったと思っています。
でも、決して簡単な道のりではありませんでした。
正直、一人で抱え込んでいたら、乗り越えるのはとても難しかったと思います。
だからこそ、ご両親やご家族など、身近な人たちとしっかり連携して、協力しながら向き合っていくことが本当に大切です。
無理をしないで、頼れるところは頼る。それが、復帰後の日々を乗り切る大きな支えになります。
保育園は何歳から預けるべき?【0歳・1歳・2歳】違いと後悔しない選び方 まとめ
- 我が家の保育園の経歴について
- 保育園の種類と違い:認可保育園と認可外保育園の特徴と選び方
- 保育園は何歳から預けられる?基本情報を確認
- 保育園は何歳から入れるのがベスト?4月入園で仕事復帰を目指す
- 出産前から準備できることを進めよう
- 保活のスケジュールや申込時期の目安
- 保育園に年度途中で入園する方法と可能性とは?
- 0歳児で保育園に入れなかったら小規模保育園を検討しよう!
- 私が子どもを保育園に預けて復帰したときの本音
- 保育園は何歳から預けるべき?【0歳・1歳・2歳】違いと後悔しない選び方 まとめ
について解説しました。
保育園選びや何歳から預けて仕事を復帰するのかなど、慌ただしい日々を送りながら決定していくのはとても大変です。
ひとりで悩まずに家族と話し合い、自身の価値観を大事にしながら決断していったくださいね。
この記事が参考になれば大変嬉しいです。

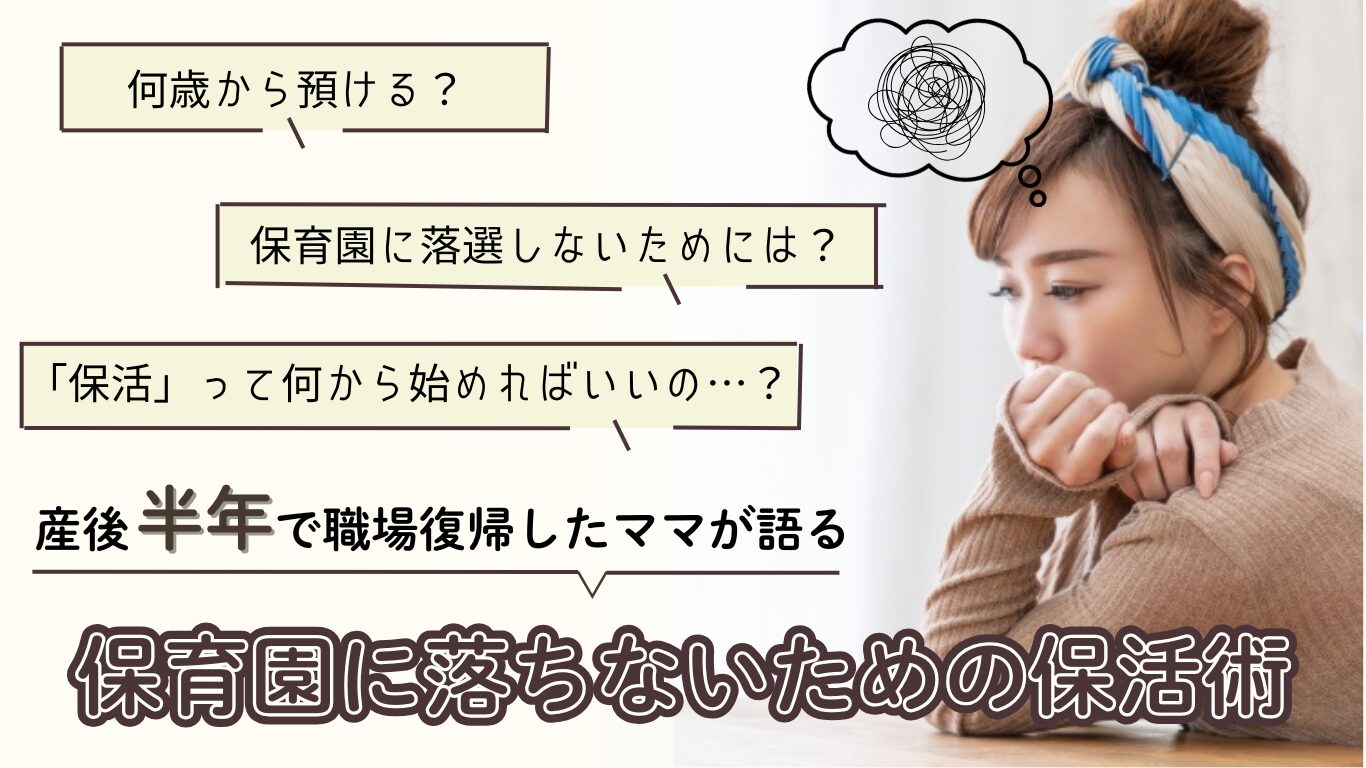



コメント